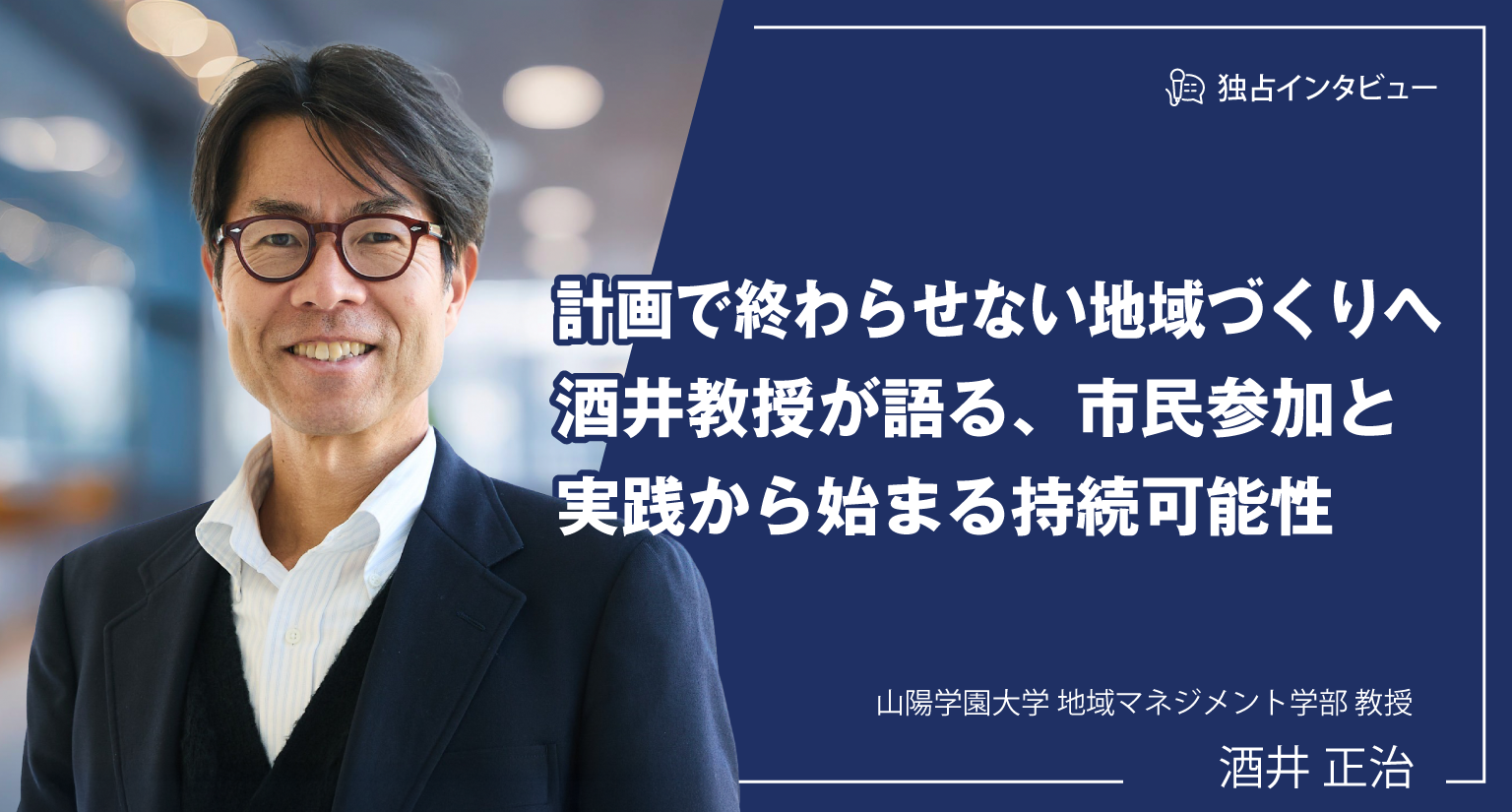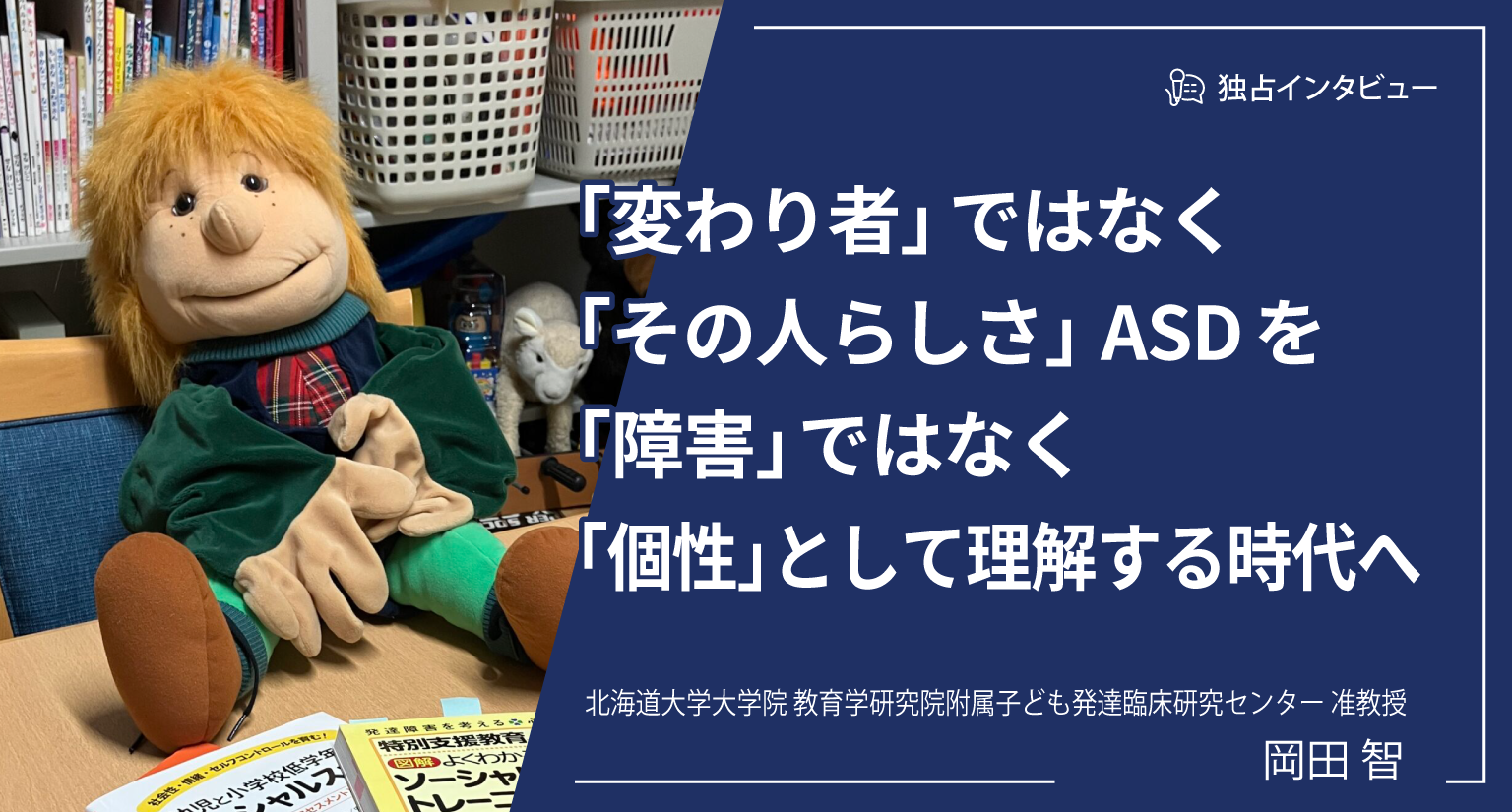がん薬物療法は数十年単位で驚くべき進化を遂げてきました。かつては戦場の恐怖だった毒ガスが、今では多くの患者に希望をもたらす抗がん薬に姿を変えています。
本インタビューでは、がん薬物療法の歴史から最新の治療法まで、岐阜薬科大学の吉村知哲教授に詳しく解説していただきました。
また、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬といった画期的な治療法や、個別化医療の現状についても触れています。さらに、副作用対策から医療費問題まで、がん薬物療法を取り巻く現実的な課題と解決に向けた取り組みも紹介しています。

吉村 知哲 / tomoaki yoshimura
岐阜薬科大学 実践薬学研究推進センター長 病院薬学研究室 教授
【プロフィール】
1985年3月 岐阜薬科大学 卒業
1987年3月 岐阜薬科大学大学院博士前期課程 修了
1987年4月 大垣市民病院薬剤部 勤務
2015年4月 大垣市民病院 薬剤部長
2017年4月 大垣市民病院 院長補佐、通院治療センター副センター長(兼務)2023年4月 岐阜薬科大学 実践薬学研究推進センター長 病院薬学研究室 教授
現在に至る
■資格
- 日本医療薬学会 がん指導薬剤師
- 日本医療薬学会 がん専門薬剤師(2007年~ 2019年)
- 日本医療薬学会 医療薬学指導薬剤師・専門薬剤
■書籍
- 「がん薬物療法副作用管理マニュアル」第3版,医学書院,2024
- 「がん専門・認定薬剤師のためのがん必須ポイント」第5版, じほう, 2023
- 「薬剤師のための栄養療法管理マニュアル」,医学書院,2023
- 「検査値と画像データから読み解く 薬効・副作用評価マニュアル」,医学書院,2022
- 「薬剤師が実践すべき副作用へのロジカルアプローチ」,南江堂,2021など
毒ガスから治療薬へ抗がん薬の基本と歴史
クリックアンドペイ(以下KL):はじめに、がん薬物療法の基本的なことから教えていただけますか。
吉村氏:がん薬物療法は、がん治療の三大治療法の一つで、他に手術療法と放射線療法があります。がん薬物療法では、抗がん薬を使用して治療を行います。以前は「抗がん剤」と呼ばれていましたが、最近では「抗がん薬」という呼び方が一般的です。
近年、免疫チェックポイント阻害薬という新しいタイプの抗がん薬が開発されたため、免疫療法を4つ目の柱として考える医療者もいます。しかし、免疫チェックポイント阻害薬も広義の抗がん薬に含まれるため、本日は免疫療法も含めた、がん薬物療法全般について説明させていただきます。
がん薬物療法の歴史は1940年代まで遡ります。最初の抗がん薬は、元々毒ガスとして使用されていたナイトロジェンマスタードでした。1946年頃からは、ナイトロジェンマスタードが白血病や悪性リンパ腫の治療薬として使用され始めています。
1950年代にはメトトレキサートやフルオロウラシル(5FU)、1970年代には白金製剤のシスプラチンなど、現在でも使用されている薬剤が開発されました。1980年代にはホルモン療法薬が乳がんや前立腺がんの治療に導入されています。
1990年代になると、分子標的薬が登場しました。1997年にリツキシマブが最初の分子標的薬として承認され、現在では多くの分子標的薬が使用されています。
2010年代には、京都大学の本庶佑教授とアメリカのジェームズ・P・アリソン博士がノーベル生理学・医学賞を受賞した研究成果に基づく免疫チェックポイント阻害薬が開発されました。2011年にアメリカでイピリムマブが承認され、2014年に日本でニボルマブが発売されています。
KL:では、がん薬物療法は主にどのような目的で使われるのでしょうか。また、がん薬物療法はどのタイミングで行われるのかについても教えていただけますか?
吉村氏:がん薬物療法の目的は大きく2つに分けられます。1つは根治(完治)を目指す治療、もう1つは延命や症状緩和を目的とする治療です。
根治を目指す治療の場合、副作用が出ても治療強度を維持することが重要です。一方、延命や症状緩和が目的の場合は、患者さんのQOL(生活の質)を保つことに重点を置きます。副作用を十分に考慮しながら治療を進め、必要に応じて抗がん薬の使用を中止したり、痛みを緩和する治療に切り替えたりします。
がん薬物療法のタイミングは、がんが手術可能かどうかによって異なります。手術可能な固形がんの場合、以下の2つのアプローチがとられます。
- 術前補助化学療法:手術前に抗がん薬を投与して腫瘍を縮小させ、手術の成功率を高めます。
- 術後補助化学療法:手術後に残存している可能性のある微小ながん細胞を除去し、再発を防ぐために行います。この治療は通常、半年から1年程度続けます。
手術不可能な進行がんや再発がんの場合は、患者さんのQOLを考慮しながら延命を目的とした治療を行います。
また、がん薬物療法の安全性を高めるため、多くの病院でレジメン登録制度が導入されています。レジメン登録制度では、各がん種に対する標準的な治療法(レジメン)が病院内で審査・登録され、医師は登録されたレジメンに従って治療を行います。
レジメンには抗がん薬の投与量、投与方法、投与間隔、点滴の投与速度、投与ルート、希釈液の種類、支持療法(副作用対策)などが詳細に規定されています。したがって、投与量や投与スケジュールの誤りによる医療事故のリスクが低減され、治療の安全性と有効性が担保されることになります。
現在では電子カルテシステムと連携し、医師がレジメン名を選択すると自動的に詳細な投与情報が展開されるようになっています。このように、がん薬物療法は安全性と効果の両面で大きく進歩しています。
狙い撃ちのがん治療 分子標的薬と免疫チェックポイント阻害薬
KL:続いて、現在では様々な種類の抗がん薬が使用されているようですが、それぞれの特徴や使い分けについて教えていただけますか。
吉村氏:がん薬物療法の抗がん薬は、現在大きく4つに分類されます。
- 殺細胞性抗がん薬(細胞障害性抗がん薬とも呼ばれる)
- 分子標的薬
- ホルモン療法薬
- 免疫チェックポイント阻害薬
殺細胞性抗がん薬は、がん細胞のDNA、RNA、タンパク合成などを阻害することでがん細胞の増殖を抑えます。作用部位によってさらに6つに分類されます:
- 代謝拮抗薬
- プラチナ製剤(白金製剤)
- アルキル化薬
- 抗腫瘍性抗生物質
- トポイソメラーゼ阻害薬
- 微小管阻害薬
今回は、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬についてお話させていただきます。分子標的薬は、がん細胞に特有の増殖や生存に必須の分子を標的として阻害します。分子標的薬は特定の分子(バイオマーカー)を発現しているがんに対して効果を発揮します。したがって、分子標的薬はバイオマーカーを基準に薬を使い分けるのが特徴です。
分子標的薬の歴史において、1997年にアメリカでリツキシマブが承認されたことは重要な出来事でした。リツキシマブはB細胞上のCD20抗原に対するモノクローナル抗体であり、悪性リンパ腫の治療効果を大幅に向上させています。
また、2001年には、小分子の分子標的薬であるイマチニブがアメリカで承認され、BCR-ABL遺伝子を標的とし、慢性骨髄性白血病(CML)の治療に用いられます。
以降も分子標的薬の開発は継続的に進み、EGFR、VEGFR、チロシンキナーゼなど、様々な分子を標的とした薬剤が開発されています。
次に、免疫チェックポイント阻害薬は、2018年にノーベル生理学・医学賞を受賞した研究に基づいて開発されました。アメリカのジェームズ・アリソン教授がCTLA-4を、京都大学の本庶佑教授がPD-1とPD-L1を発見しています。
免疫チェックポイント阻害薬は、体の免疫抑制機能に関わる分子を標的とします。免疫抑制機能はがん細胞が免疫反応を回避して増殖するのを助けているため、免疫チェックポイント阻害薬は免疫抑制機能を抑制することで、がん細胞に対する免疫反応を高めます。
日本では現在、以下の免疫チェックポイント阻害薬が使用されています。
- PD-1標的:ニボルマブ、ペンブロリズマブ、セミプリマブ
- PD-L1標的:アベルマブ、アテゾリズマブ、デュルバルマブ
- CTLA-4標的:イピリムマブ、トレメリムマブ
また、抗がん薬の副作用を抑える支持療法薬も開発が進んでいます。特に悪心・嘔吐に対する制吐薬は、以下の4種類が主に使用されています。
- ステロイドホルモン(デキサメタゾン)
- 5-HT3受容体拮抗薬
- NK1受容体拮抗薬
- オランザピン(抗精神病薬)
これらの制吐薬を適切に組み合わせることで、抗がん薬の副作用管理が改善されています。
KL:がん薬物療法の実例や、治療後の患者さんの満足度について教えていただけますか。
吉村氏:がん薬物療法の実施にあたっては、各がん種ごとに治療ガイドラインが作成されています。例えば、肺がん治療ガイドラインや大腸がん治療ガイドラインなどがあります。これらのガイドラインは、これまでの臨床試験や治療成績をもとに、どのような患者さんにどの抗がん薬を使用すべきかを示しています。現在では、患者さんの遺伝子変異なども考慮しながら治療方針を決定しています。
大腸がんを例に挙げると、切除不能な進行再発大腸がんの治療方針は、大腸がん治療ガイドラインに記載されています。治療は一次治療、二次治療、三次治療と段階的に行われます。
一次治療では、例えばFOLFOX療法(フルオロウラシル、レボホリナート、オキサリプラチンの3剤併用)にベバシズマブ(血管新生阻害薬)を加えた治療が行われます。
治療効果が得られなくなった場合、二次治療に移行します。二次治療では、FOLFOXのオキサリプラチンをイリノテカン(トポイソメラーゼ阻害薬)に変更したFOLFIRI療法を行います。さらに、患者さんの遺伝子変異を考慮して、RAS遺伝子が野生型の場合は抗EGFR抗体薬(セツキシマブやパニツムマブ)を併用することがあります。
このように、患者さんの個別の特性に応じて治療が展開される「個別化医療」が現在の主流となっています。
次に、患者さんの満足度については、治療効果が得られれば高くなりますが、副作用の発現により低下することがあります。近年、制吐薬などの支持療法薬の開発により、悪心・嘔吐などの副作用に関する満足度は向上しています。
しかし、脱毛や神経障害など、対処が難しい副作用もあります。例えば、オキサリプラチンによる末梢神経障害は、手の細かな動作が困難になるなど日常生活に支障をきたす可能性があります。このような副作用は治療終了後も長期間続くことがあり、患者さんのQOL(生活の質)を低下させる要因となります。
脱毛に対してはウィッグや帽子の使用で対処しますが、神経障害に対しては有効な治療法が限られているのが現状です。
このように、治療内容によって患者さんの満足度は異なり、治療効果と副作用のバランスが重要となります。医療者は患者さんの苦痛を軽減しつつ、最適な治療を提供することを目指しています。
抗がん薬の課題 副作用と廃棄問題
KL:では最後の質問になりますが、がん薬物療法における現在の課題点や、先生なりの対策方法について教えてください。
吉村氏:薬剤師の立場から、病院での経験を基に2つの課題を挙げさせていただきます。
1つ目は副作用対策です。チーム医療の中で、医師を中心に看護師や薬剤師が協力していますが、薬剤師の重要な役割の一つは副作用を未然に防ぎ、軽減することです。薬剤師も治療に参画し、必要な提案をしていますが、副作用を抑える上では限界があります。
私たちの目標は、副作用で治療を中断する患者を減らすことです。治療が順調に進めば、がんが治ったり延命につながりますが、副作用で治療が中止になれば、治療効果は落ちてしまいます。したがって、治療の継続性を高めることが、薬剤師の重要な役割であるといえるでしょう。
例えば、経口抗がん薬の場合、患者自身が体調を見ながら服用するため、薬剤師が患者と向き合い、副作用対策や休薬のタイミングなどを一緒に考えています。
私が勤務していた大垣市民病院では、経口抗がん薬を服用している患者に対し、医師の診察前に薬剤師が面談を行う「薬剤師外来」を実施しています。がん専門薬剤師が患者の服薬状況や副作用の状況を聞き、支持療法薬の処方提案や減量の提案などを電子カルテに記載し、医師に伝えます。医師は電子カルテの情報を参考に、処方や用量調整を行います。
このような活動のアウトカムとして、薬剤師が関わることで1年間抗がん薬を継続服用できる患者の割合が有意に向上したというデータも出ています。
2つ目の課題は、抗がん薬の高額化に伴う医療費の問題です。特に、抗がん薬の廃棄問題が社会問題となっています。多くの抗がん薬は、患者の体格に応じて投与量が決まります。例えば、体重1kgあたり3mgを投与する薬の場合、50kgの患者なら150mg必要です。しかし、薬剤のバイアルは100mgという規格で提供されることが多く、150mgを使用するために200mgを購入し、50mgを廃棄することになります。
現在の医療制度では、使用量ではなくバイアル単位で請求するため、実際に使用した量以上の請求が行われ、廃棄される薬剤の量も増えています。薬剤の廃棄量は金額にして年間500億円から700億円に上るという試算もあります。
このような、薬剤の廃棄問題に対して、様々な対策を検討しています。まず、残った薬剤を他の患者に使用する「使い回し」の方法があります。次に、実際の使用量に基づく請求方式への変更も考えています。また、製薬会社へ小容量規格の製造を依頼することで、廃棄量を減らすこともできます。さらに、抗がん薬調製ロボットの導入によっても廃棄量の削減が期待できます。
大垣市民病院では、すでに抗がん薬調製ロボットを導入し、余った薬剤の使い回しが可能な機能を活用しています。これらの取り組みはまだ実験段階ですが、少しでも廃棄量を減らすよう努力を続けています。このように、医療費の削減と効率的な薬剤使用を目指して、様々な対策が進められています。