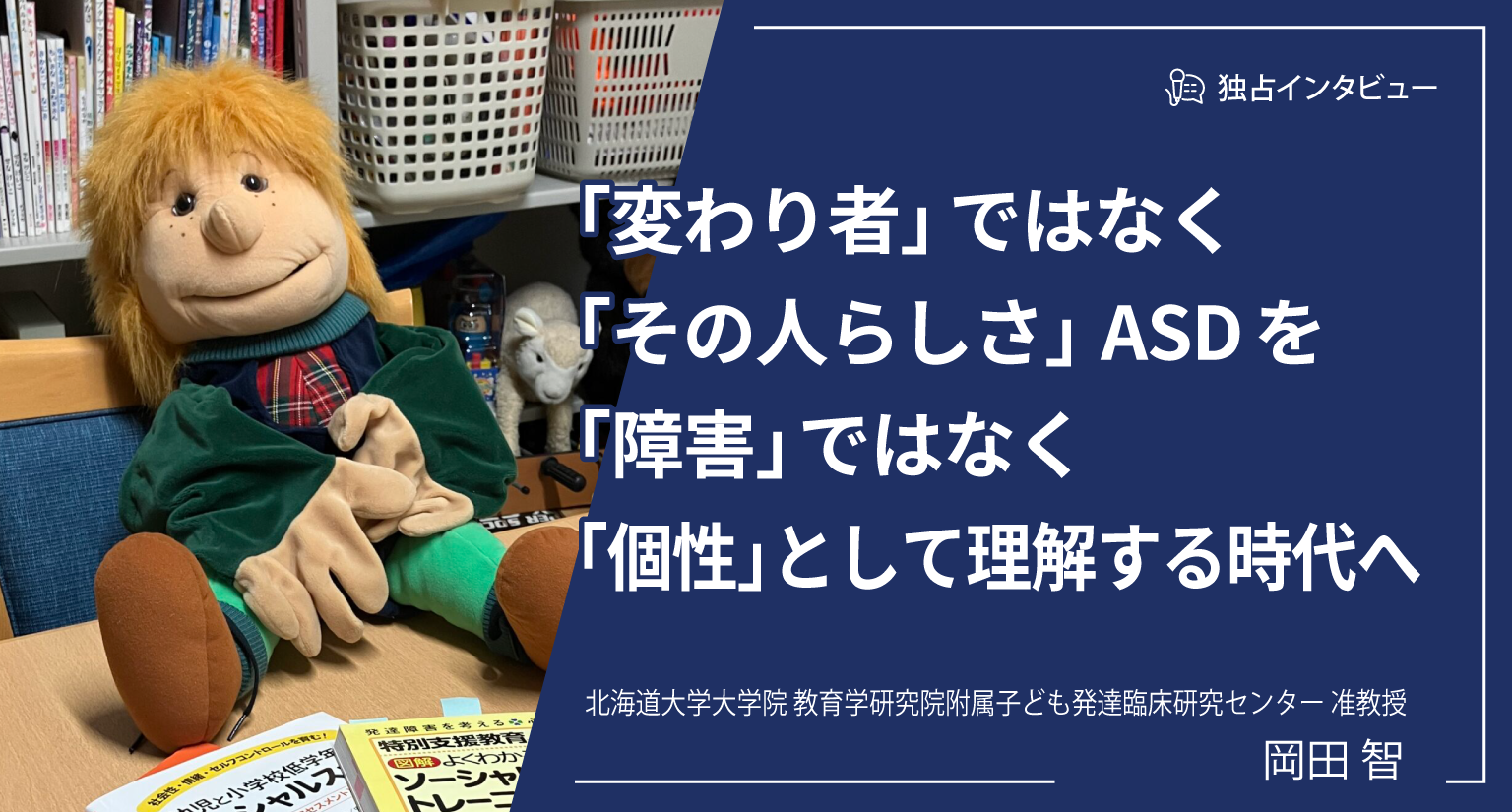英語が国際共通語として圧倒的な地位を占める現代では、日本の英語教育も急速な改革が求められています。国際社会での競争力を維持するためにも英語力の向上は不可欠です。しかし、日本の英語力は2024年の調査で、非英語圏116カ国中92位と低迷しています。
この記事では、英語教育が日本の未来にどのように影響するのか、現行の教育制度が直面している課題や改善策について、松本大学の大石文朗教授から伺いました。

大石 文朗 / Fumio Oishi
松本大学 教育学部 学校教育学科 教授
【プロフィール】
兵庫県に生まれる。
米国University of Hawaii at Manoa経済学部卒業(BA取得)。
米国San Francisco State University大学院教育学研究科修了(MA取得)。
名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士前期課程修了(修士号取得)。
名古屋市立大学大学院人間文化研究科博士後期課程修了(博士号取得)。
米国NPO法人留学支援機関にて所長として米国駐在勤務の後、愛知江南短期大学教授、金城学院大学教授を経て、現在は松本大学教授。
専門分野は言語(英語)文化教育。
英語が国際共通語となった背景と日本の対応
クリックアンドペイ(以下KL):はじめに、英語学習が小学校から必修科目になった背景について、教えていただけないでしょうか。
大石氏:結論から申し上げると、英語という言語が国際共通語的な役割を果たす唯一無二の言語になったことが、英語学習が小学校から必修科目になった1番の原因だと思います。
英語のできる人材を育てないと、国際的な地位が保てなくて国益を損ねかねない、という考えが公教育に反映されたものだと思います。
特に非英語圏の国にとっては、国際舞台で円滑なコミュニケーションを取るための英語教育は、切実な課題です。過去を振り返ると2000年1月に「21世紀日本の構想」懇談会がありました。当時の首相である小渕恵三内閣総理大臣が「英語の第二公用語化」を提言したことがありました。
当然、この提言は物議を醸しましたが、そのような提言がなされた当時の社会的背景として、今後ますます世界各国の相互依存が高まって、諸外国との相互理解が日本の存在を左右しかねないという国際状況があったのだと思います。特に情報通信の世界においては、国境という概念すら希薄になっています。
2000年頃は、インターネットやWindows 98などのパソコンが浸透してきた時期で、瞬時に情報交換が可能になった頃でした。IT産業という言葉がまだ定着していなくても、今後さらなる通信技術の発展に伴って世界がますます狭くなっていくということは、容易に想像できたと思います。そして他民族との物理的・心理的距離感が短くなって、良かれ悪しかれ互いの影響力が強まるというふうに考えられた頃だと思います。
また、世界には大体4,000~5,000(6,000という人もいますが)の言語があります。では、なぜ英語が国際共通語として特別重要な言語になったのかについて話したいと思います。
そもそも英語が圧倒的な国際共通語的言語になったのは、第二次世界大戦以降だと言われています。戦前はアカデミックな分野はドイツ語、外交に関してはフランス語、そしてビジネスでは英語という緩やかな言語的な役割分担がありました。
また、戦後しばらくの間、日本の大学入試でも第二外国語まで受験させていましたし、大学のカリキュラムでも第二外国語まで必修科目になっていました。しかし現在、大学はもとより大学院入試でも多くの場合、英語のみで受験が可能になっています。また、大半の大学では第二外国語の履修に関しては選択科目扱いになっているのが現状です。
KL:では、なぜ英語が国際共通語として特別な言語になったのでしょうか。
大石氏:まず挙げられるのは、世界における英語使用人口の多さです。現在、英語を公用語や準公用語にしている人口は約20億人と言われています。世界の人口は最近までは65億と言われていましたが、今80億と言われているようです。世界の人口を80億人とすると、4分の1の人口が英語を使用しているわけです。
人口の多さというと中国を思い浮かべると思いますが、中国は言語が単一ではありません。北京語や広東語、上海語などの違いがあります。方言というよりは違う言語のような状況です。したがって、言語使用の人口という点では、英語が世界で一番多く使われている言語となっています。
さらに、単に使用人口が多いだけではなく、国際社会を牽引する重要な専門分野で独占的に英語が使用されている状況が、英語を特別重要なものにしています。その結果、強制的あるいは半強制的に使用人口を増やしているという側面があります。
例えば、国際政治の中核と言える国際連合の公用語は、英語の他にアラビア語、中国語、フランス語、ロシア語、スペイン語の6カ国語に限られています。しかし、公式文書作成用語になると英語、フランス語、ロシア語、スペイン語という西洋語に限定されています。さらに、これらの言語の中で、英語とフランス語が主要言語となっていて、国連文書の約90パーセントは英語で記されていると言われています。
その結果、国連加盟国のおよそ40パーセントは、自国語を使えないのが現状です。つまり、会議の発言や国連の記録を理解するためには、これらの西洋語、特に英語に熟達していなければならないという現実が、非西洋圏の人々の前に立ちはだかっているということになります。
KL:学術分野における英語の影響力はいかがでしょうか。
大石氏:学問の領域でも英語が共通語として使われています。英語圏の学者たちが会議の主導権を握りやすく、非英語圏の学者たちは不平等な言語状況に置かれているという指摘があります。また、学術論文に関しても、分野によっては世界の約95パーセントが英語で書かれているとも言われています。
つまり、国際的な学術刊行物のほとんどが、現在、英語で出版されているのです。国際的に評価されるためには英語で論文を書く必要があるということです。
さらに、英語の優位性を後押ししたのがIT関連産業です。世界のコンピューターに収められている情報の約9割強は英語を媒体としていると言われています。そして米国発祥の大手企業、いわゆるGAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft)が世界中で利用されています。
航空業界や海運業界でも英語が主要言語です。世界的な催し物であるオリンピックでも英語が主要言語になります。世界5大放送局と言われるCBS、NBC、ABC、BBC、CBCは、常時数億人以上の視聴者に対して英語で放送を行っています。
このように、英語の世界的な優位性を挙げればきりがありません。特にコンピューターにより新たなコミュニケーション手段で圧倒的な優位性を築き上げた英語は、今以上に世界的規模で使用人口が増えていくことが予想されます。このような予想は、非英語圏の民族にとってコミュニケーション難民に陥る可能性があることを意味しています。
こうした世界的な背景を受けて、現在のアジアにおける英語の扱いは、強制的に後押しされたものではなく、自ら学ぶという積極的かつ能動的なものであると、指摘する研究者もいるほどです。言語使用の拡大という視点から歴史を辿っていくと、支配者が被支配者に自らの言語を押し付けたもので、英語がもともと広がったのは植民地支配によるものであり、それはしばしば英国やアメリカの文化帝国主義とも呼ばれています。
しかし、現在ではむしろ、アジアの人たちは英語を積極的に自ら学ぼうとしている状況に置かれています。例えば、ASEAN(東南アジア諸国連合)は英語を国際語として普及するために、1968年にはすでにシンガポールに地域英語センターを設立しています。もちろんシンガポールは英語を公用語として使用している国です。
加えて、全世界にある非英語圏の76パーセントの子供たちが、英語を学んでいるとも言われています。
日本の英語教育改革と小学校での取り組み
KL:日本の英語教育の現状はどうなっているのでしょうか?
大石氏:英語が世界で圧倒的な地位を占めると、将来の日本を担う人材を育てる公教育に当然影響を及ぼします。さらに、日本人の英語力の国際比較がこの状況に拍車をかけています。
2024年にスイスの教育機関が発表した調査によれば、日本の英語力は、非英語圏116カ国中92位で、5段階評価の下から2番目という低いレベルにあります。2000年当時も日本の英語力は低く、英語力を向上させる必要性が強く認識されていました。
このような背景が、公立小学校での英語学習導入に影響を与えたと考えます。2002年度から施行された小学校学習指導要領では、「総合的な学習の時間」に公立小学校3年生以上を対象として、国際理解教育の一環として「外国語会話」が取り入れられています。これは英語の学習開始年齢を引き下げるもので、戦後最大の英語教育改革として注目されました。
また、2000年頃からは学習指導要領の移行期として、各学校の裁量で英語活動を行うことが可能になりました。「総合的な学習の時間」は本来、環境、情報、福祉・健康、国際理解など多様な分野から授業担当者がテーマを選び、教材や指導方法を教師が工夫して作り上げるものです。しかし、多くの学校が英会話などを扱い始めたのが実情です。
さらに英語学習を加速させるため、2020年度以降は英語学習の開始が中学ではなく小学校となりました。小学3・4年生では「外国語活動」として、小学5・6年生では正式な「教科」として英語が導入されています。ただし、学習指導要領の外国語部分は大きな変更であったため、2018年度から先行実施の期間が設けられました。その結果、2018年度以降は、多くの公立小学校で3年生以上が英語に触れる機会が増えています。
これまで説明してきたように、戦後、英語は国際共通語としての地位を確立し、国益を考えると英語に堪能な人材を育てる必要があります。さらに、日本人の英語力はアジア近隣の非英語圏諸国と比較しても遅れを取っているという焦りもあります。これらが、英語学習が公立小学校で必修科目になった背景だと思います。
早期英語教育の効果と専門家の見解
KL:では、英語教育を行うことでどのような効果が得られるのでしょうか。
大石氏:英語教育の効果を検証するのは非常に難しい課題です。なぜなら、教育効果には多くの要因が複雑に絡み合っているからです。
英語教育のあり方はもちろん、個人の性格、生活環境、周囲の人々の影響、そして時代の雰囲気まで、様々な要素が学習者の英語に対するモチベーションを左右します。その結果、個々人の英語力にも差が生じます。このような複雑性から、早期英語教育に関しては賛成派と反対派に分かれています。
まず、賛成派の主張から見ていきましょう。彼らの模範となっているのが、カナダのイマージョン教育です。カナダは1969年に英語とフランス語を公用語と定め、早期からのバイリンガル教育に国を挙げて取り組んでいます。
イマージョン教育の理論的基盤となったのが、「言語習得の臨界期説」です。カナダの研究者ワルダー・ペンフィールドによると、4歳から10歳が言語習得に最適な年齢だとされています。この時期を過ぎると、脳の言語習得能力が徐々に低下すると考えられています。
ただし、年齢と言語習得の関係については様々な見解があります。例えば、2歳から4歳までの間に無理に2言語を強いると、言語発達が遅れる可能性があるという研究結果もあります。
カナダのバイリンガル教育研究の第一人者、カミンズ教授は「2言語共有説」を提唱しています。これは、2つの言語が脳内で部分的に共有されているため、同時に習得可能だとする考え方です。特に、高度な認知能力を要する場面では、既存の言語知識が新しい言語の学習に役立つとされています。
KL:反対派の意見はどのようなものでしょうか。
大石氏:早期英語教育に反対する立場の人々は、「2言語バランス説」を支持する傾向にあります。2言語バランス説によると、脳の言語処理能力には限りがあるため、2つの言語を同時に習得すると、どちらも中途半端になる可能性があるとされています。
反対派は、まず母語教育を優先すべきだと主張します。その理由として、以下の点が挙げられます。
- 言語は高度な概念理解の手段であり、確固とした言語基盤がないと学力形成に支障をきたす可能性がある。
- 言語習得は文化的アイデンティティと密接に関連しているため、早期の2言語教育がアイデンティティの形成を阻害する恐れがある。
2言語教育は、本来、米国やカナダのような移民国家で、社会適応のために必要とされた教育形態です。特にカナダでは、国の制度として公用語を定めたことで、バイリンガル教育に関する研究が盛んに行われています。
日本で早期英語教育を検討する場合、その利点だけでなく課題もよく理解した上で取り組むことが重要です。また、実績のある教育機関を参考にするのも一案です。
バイリンガル教育を評価する際は、その形態の違いにも注目する必要があります。例えば、カナダのイマージョン教育は2言語の自在な操作を目指すのに対し、米国の「トランジショナル」バイリンガル教育は、英語以外の言語から英語への移行を支援することを目的としています。
早期英語教育の実態と調査結果から見える現状
KL:日本での早期英語教育の効果についての研究はありますか?
大石氏:日本人に関する早期英語教育やバイリンガル教育に関する研究自体が少ないのが現状です。教育と効果の因果関係が特定しにくく、複雑に絡み合っているため、研究が難しくなっています。
早期英語教育がもたらした効果を正確に測るには、同一人物を長期にわたって追跡調査する必要があります。
ただ、早期英語教育の効果の手がかりになる可能性のある研究として、2009年度にベネッセ教育総合研究所が日本全国の公立中学校の2年生を対象に行ったアンケート調査があります。2,967名の有効回答を得て、英語学力、外国への親しみ、グローバル人材意識に関して調査しました。結果は以下の通りです。
- 英語学力については小学校英語の開始時期が早いほど、英語学力が高い傾向が確認できました。ただし、地域によっては学校外の英語教育も受けているため、小学校英語教育の早期化だけがもたらした効果かどうかは定かではありません。
- 外国への親しみとグローバル人材意識については、小学校英語教育の早期化が親しみを養成するとは言えないという結論に至っています。ただし、将来的に教育効果が発揮される可能性があるため、長期にわたる同一人物の追跡調査が必要だと指摘されています。
現時点では、公立小学校での英語教育も手探り状態で、教科担任制も検討されています。本当に早期英語教育を望む親御さんは、私立学校を選択するか、独自の判断で決断していく必要があります。
早期英語教育の効果については、2002年度から本格的に始まったばかりで、効果の研究自体もあまり進んでいません。また、公立小学校での早期化がもたらした効果なのかどうかも、様々な要因が複雑に絡み合っているため、明確にはわかっていないのが現状です。
日本の英語教育の課題と海外の成功例に学ぶ改善策
KL:複雑な要因が絡み合っているため、正確な効果の把握が難しいことはわかりました。反対に、現在の早期英語教育における問題点と、問題点に対する改善案があれば教えていただけますか。
大石氏:日本の現代の早期英語教育の問題点を明らかにするために、まずカナダのイマージョン型バイリンガル教育の成功要因を見ていきたいと思います。成功しているところがなぜ成功したのかという要因が分かれば、日本の英語教育に足りないところが見えてくると思います。
紹介する成功要因は中島和子教授が指摘したものです。中島教授はトロント大学に勤務していた方で、先ほど紹介した2言語共有説のカミンズ教授とも親交がありました。中島教授はカミンズ教授のお弟子さんだと私は聞いています。私も大学院生時代に直接中島教授から講義を受けたことがあります。
中島教授が挙げた成功要因は7つあります。
- 1つ目は、言葉の使い分けがはっきりしていることです。フランス語を使う教室や教師、英語を使う教室や教師が決まっています。学校の中で使い分けのしつけがされます。このことによって教師と子供が接する場合には、1言語でのコミュニケーションになります。子供が混乱することはありません。言語は場に支配されるので、状況によって言語を切り替えることを体に覚えさせています。
- 2つ目は、言語の接触量が圧倒的に多いということです。トータルイマージョン教育の場合、全体で約5,000時間の接触量を与えるプログラムを組んでいます。
- 3つ目は、押し付けられた強制的な2言語教育ではないということです。イマージョン教育を受けるかどうかは、当人や親の選択に任されています。
- 4つ目は、教授法が機能的アプローチを実践していることです。コミュニケーションの道具として言語を捉えます。完全に自然習得に任せており、文化や文法を分析的に教えることはしません。教科の内容が理解できるかどうかに焦点が絞られます。
- 5つ目は、言語が教科学習のツールとして使われていることです。高度な認知学力面の外国語習得につながっています。
- 6つ目は、親、教師、社会が三位一体で2言語を同時に伸ばそうとする姿勢を持っていることです。バイリンガル教育を受けることの価値が社会一般で認められており、ネイティブに近い2言語を身につけることが望ましいと思われています。
- 7つ目は、小学校、中学校、高校、大学と2言語教育が一貫して続けられるように教育体制が整えられていることです。
これらの7つの成功要因と対比すると、日本の現在の早期英語教育には、多くの問題点があります。しかし、最も大きな問題点は、何のために早期英語教育を日本で行うのかということが曖昧なことだと私は考えています。
本来、2言語教育は、移民で成り立った米国やカナダのように、新たな社会に同化するために日常生活で必要だから行われてきたものです。しかし、日本では一般的な人々が日常生活で英語を使用する場面はほとんどありません。
では、なぜ公立小学校で英語が教科になるほど早期化してまで英語教育に力を入れているのでしょうか。それは、英語が小学校から必修科目になった背景で説明したように、今後ますますグローバル化が進み、国際共通語である英語に長けた人材が必要だからです。
ここでポイントになるのが、全ての人がグローバルの最前線に行くことはないということです。例えば、ピアノを幼い頃から学んでいても、将来全ての人がピアノに携わる仕事をするわけではありません。しかし、中には継続してピアノの勉強を行い、音楽関連の職に就く人も出てきます。
音楽の才能があっても、音楽に触れる機会がなければ、その人の才能は開花しません。同様に、英語の才能があっても、英語という言語に触れなければ、一生英語はできません。
公立小学校での英語教育の価値は、言語習得というよりは、むしろ「こんな世界もあるんだ」と気づかせることにこそあるのではないかと私は考えています。
小学校3年生・4年生の外国語活動は週に1コマで、年間35時間相当です。小学校5年生・6年生の英語の授業は週2コマで、年間70時間です。このくらいの時間数では、言語習得の面では十分ではありません。先ほど申し上げたように、トータルイマージョンの場合は5,000時間なので、現状の時間数ではそれには程遠いです。
しかし、ピアノの例で挙げたように、全ての人が英語に長けた人になる必要はありません。それぞれの興味で自らの道に進んでいった方がよいですし、米国やカナダと違って、日本では英語ができないから生活に困るということはありません。
このように、公立小学校の英語教育は早期に英語に触れて自分の向き不向きに気づくということで、今のところ他の教科とのバランスを考えれば、私は肯定的に捉えています。
ただし、現状に甘んじていてはさらなる進歩がないと思いますので、英語に長けたグローバル人材を養成することは大変重要な課題です。私なりの改善点というよりは、希望も含めた3点を挙げたいと思います。
- 1つ目は、英語に関して興味を持ってバイリンガルを目指す人たちに対して、教育の選択肢をもっと広げてほしいということです。現時点でもイマージョン教育を行っている私立学校はありますが、少数で授業料が高額です。また、インターナショナルスクールに進む人もいますが、日本の大学受験先が制限されます。法整備も含めて、様々な選択肢を社会が応援して整備してほしいと思います。
- 2つ目は、インバウンドの外国人が増えていることに関連して、英語教育は言語コミュニケーションという言語習得に目が行きやすいのですが、むしろ多様な人々に対しての寛容性を育む異文化理解にもっと力を入れてほしいということです。小学校、中学校、高校において継続的な教育の時間を設けてほしいと思います。特に、小学校高学年になると意識の高い親ほど中学受験のための英語教育に注力し始め、その後高校受験、大学受験と受験対策の英語教育が重視されていきます。だからこそ、他の文化についてもっと学ぶ機会が設けられればよいと思います。
- 3つ目は、人と違うことにチャレンジした人を評価する社会であってほしいということです。バイリンガル教育が定着するためには、バイリンガル教育を受けることの価値が社会一般で認められ、ネイティブに近い2言語を身につけることが望ましいと思われている下地が必要です。しかし、現在の日本では、バイリンガル教育はごく一部の限られた人が進んでいく選択肢です。人とは違うバイリンガル教育を選んだ人をもっと評価する社会であってほしいです。そうすれば、英語習得に興味を持って自ら進んでバイリンガルになりたいという人材が育っていくのではないかと思います。
以上が私の改善案というか希望です。
グローバル起業家に求められる英語力とマインドセット
KL:このインタビューを読む読者は、起業家志望の学生が多いです。そのような学生に対してアドバイスをお願いできますか。
大石氏:アドバイスというと少し大げさですが、私の10数年間の米国滞在経験と30年間以上大学で教鞭を執り、学生の就職活動をみてきた経験から、私なりの考えを紹介したいと思います。
まず、なぜ起業を目指すのかの自己分析を行ってほしいということです。自分自身のモチベーションはもちろん、自身が置かれている生活環境や日本社会の現状も含めて分析してください。
単にビル・ゲイツやスティーブ・ジョブズなどの伝記を読んで感化されたり、ポール・グレアムのような成功事例という光の部分だけを見ていてはいけません。必ず物事には光があれば影が存在します。
レオナルド・ダ・ヴィンチも美しい人の美しさを描くために、人の醜い表情も観察してデッサンに残しています。同じように、起業家の光である成功者ばかりを見ていては正当な判断はできません。
成功者よりもはるかに多くの失敗者がいて、成功者も多くの困難を乗り越えてたどり着いているのです。
米国での起業は参考にはなりますが、そのまま日本に当てはまらないと私は思っています。米国は本当に個人主義が定着しています。個人主義は教育にも反映されており、小学校から大学まで貫かれています。自分の考えが求められ、小論文課題などでは人と違う視点に加点されます。教科書に書いてあるようなことを書いても「C」評価で、いい点数はもらえません。
ただし、単に独りよがりな思いつきではダメで、納得させる根拠が伴っていることが必要です。このことは投資文化へも影響していると私は考えています。人と違うユニークな事業に対して納得させる根拠があれば投資してくれるのです。
他方、日本の場合、人と違うことに対して不安を抱き、レールから外れることを極端に恐れる傾向があります。同じようなリクルートスーツに身を固めて、同じような時期に就職活動を始めます。そして、有名大企業や公務員を目指す人たちが多いのが現状です。
企業側も新卒一括採用がいまだに主流です。ジョブ型雇用という言葉が出てきていますが、まだ一部の取り組みに過ぎません。数十年前までは、特に大企業では中途採用枠は存在しないところもありました。
起業は将来の日本を変える礎になるかもしれませんが、現状ではまだまだ米国ほど社会的なインフラが整っていませんし、起業を評価する文化が定着していません。よほどの結果を出さない限り、評価されにくいという現状があります。
無責任に「起業頑張ってください」というのは簡単ですが、老婆心ながら、起業の影の部分を承知の上で、それでも自分は起業するんだという人は進んだ方がいいと思います。その意思こそがその人の個性だと思うのです。
個性とは、たたかれてもたたかれても頭を持ち上げるものだと私は考えています。
周りから起業に対して否定的な意見を言われても、体の芯から湧き上がるものがある人は、起業の世界に飛び込んでしまうでしょう。逆に、そのような情熱がない限り、起業は甘い世界ではありません。
これは日本の早期英語教育にも言えることかもしれません。小学校からイマージョン教育の学校やインターナショナルスクールへ入学する日本人も少なからずいます。人と違う道を選択するという意味では、起業と通じるところがあるかもしれません。
本当に起業したい人は、体から湧き上がる情熱を持ち合わせているのではないかと思います。
これが私の考えです。参考になるかどうかわかりませんが、以上です。
参照資料:
*中嶋和子「バイリンガル教育の方法」
*豊永耕平、須藤康介「小学校英語教育の効果に関する研究」
*津田幸男「英語支配の構造」
*「日本人の英語力、非英語圏で92位に後退:スイスの教育機関2024年調査」
https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02199