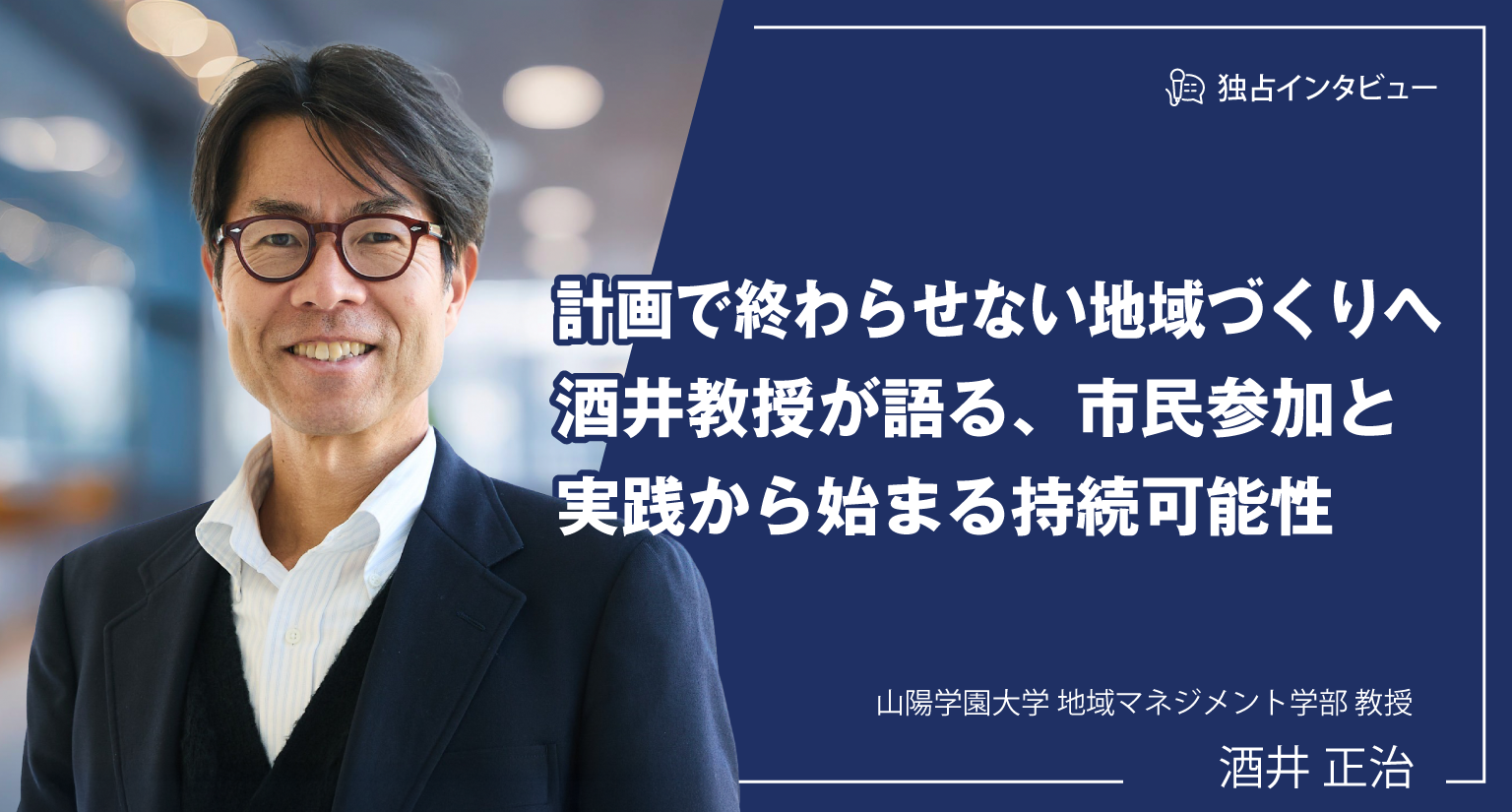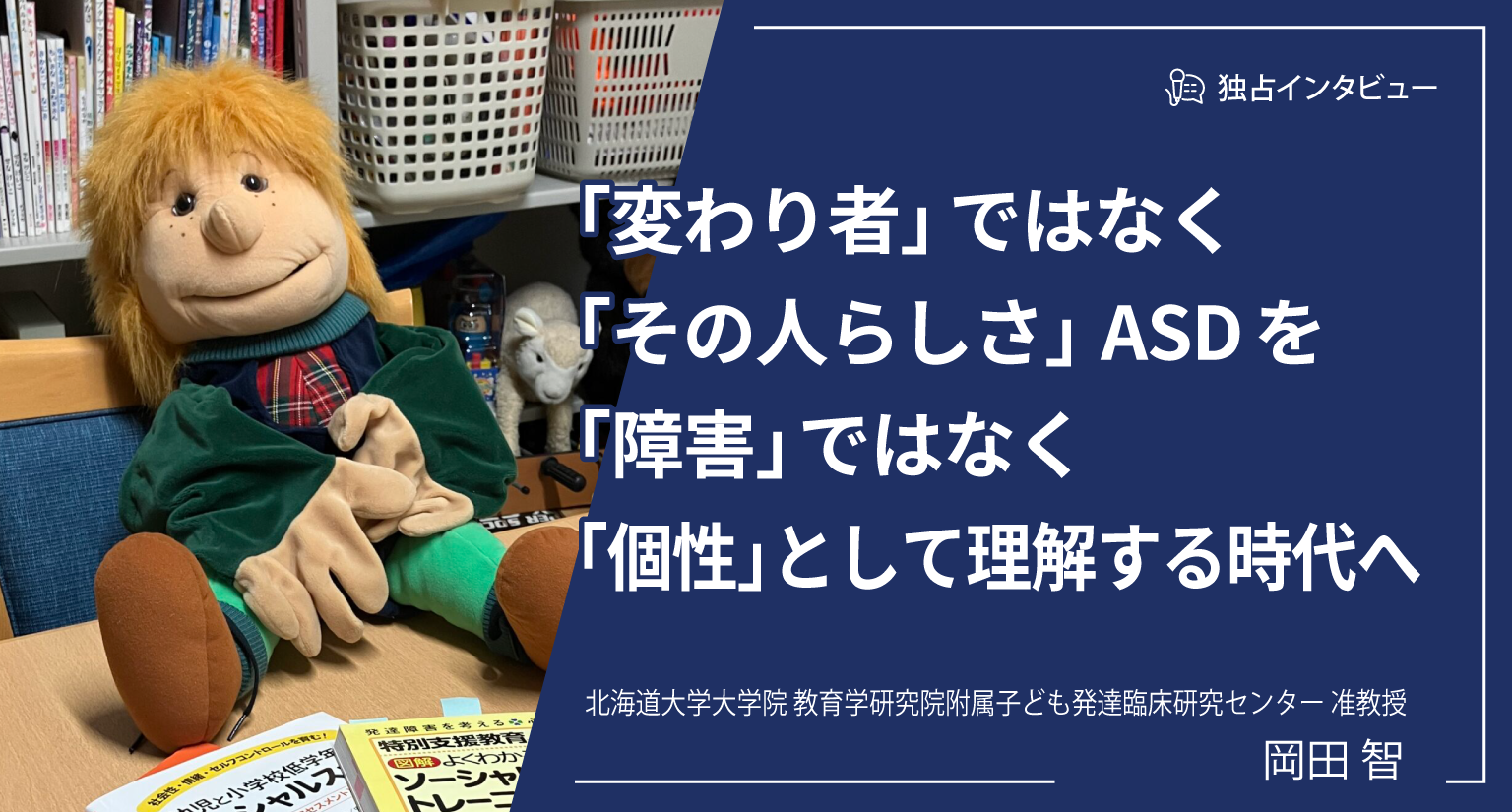日本の刑事司法制度において、冤罪が長年にわたり重要な課題となっています。有罪率99.9%という数字の裏側にある現実とは何か。なぜ無実の人が罪に問われることがあるのか。そして、どうすれば冤罪を防ぐことができるのか。このような複雑な問題について、刑事手続の専門家である北九州市立大学の水野陽一准教授にお話を伺いました。

水野 陽一 / yoichi mizuno
北九州市立大学 法学部法律学科 教授
【プロフィール】
弁護士になるつもりで勉強していましたが、気づけば刑法ばかり勉強している日々でした。今の師匠と出会い、研究者を勧められ、幅広い視野を持って研究するため刑事訴訟法や刑事政策の研究も進めてきました。研究の道へ進むのが決定的となったのはドイツ学術交流会の支援を受けたドイツへの留学で、ここで他の分野の研究者と交流を持つことができたことは非常に大きな経験となりました。元々音楽が大好きだったので、ドイツに修行に来ている音楽家とも交流する機会があり、音楽趣味に拍車がかかりました。なんとか広島大学で博士号を取ることもでき、北九大に着任して10年が経とうとしています。
有罪率99.9%の現実とその影響
クリックアンドペイ(以下KL):はじめに、 冤罪が起きてしまう理由について教えてください。
水野氏: はい、冤罪が起きてしまう最悪なパターンとして、捜査機関と訴追機関である警察や検察が意図的に冤罪を起こすケースがあります。何らかの理由で特定の人を犯人に仕立て上げるようなことが、過去にも報告されています。しかし、このようなケースは稀です。ところで、日本の刑事司法における有罪率についてご存知ですか?
KL:わかりませんが、ドラマなどで有罪率が高いとは聞いたことがあります。
水野氏:そうですね。よく言われているのは99.9%が有罪になるということです。有罪率が99.9%ということについて、良いことだと思いますか、それとも悪いことだと思いますか?
KL:難しいですね。裁判をすることでほぼ確実に有罪になってしまうのであれば、裁判をする必要がないのではないかとも考えます。
水野氏:そうですね。有罪、無罪は裁判での審理を中心に決めるべきだと考える人が増えてくれば、冤罪は減る可能性があります。しかし、これまでの日本では、「99.9%の有罪率」は警察と検察の優秀さを示す数字だと説明されてきました。
これを「精密司法」と呼び、裁判になる前に無罪の人はすでに除外されているという考え方です。警察が捜査し、検察がそれを確認することで、無罪の人は正確に裁判から外されるため、裁判にかかった人はほとんどが有罪になるという考え方ですね。
裁判官も、警察と検察がちゃんとやっているだろうという前提で判断しがちになるため、本来なら無罪の可能性を疑ってかかるべきなのに、「裁判に来たら99.9%有罪になるのだから、この事件も有罪だろう」という考えから出発してしまう可能性もあるわけですね。
このような事情から、本来無罪になるべき人が裁判にかけられた場合、無罪の事実が発見されにくくなり、冤罪が起こっているのではないかとの指摘もされています。
日本最大の冤罪事件
KL:日本最大の冤罪事件について、教えてください。
水野氏:まず、日本の冤罪事件の「最大」をどう定義するのかが難しいのですが、いくつかの観点から重要な事例を挙げることができます。
巻き込まれた人数が最も多い事件:松川事件(1949年)
松川事件は、戦後間もない1949年に起きた旧国鉄の列車転覆事故に関する冤罪事件です。松川事件の背景には、当時の労使関係の緊張があったとされています。警察は労働組合の関与を疑い、その線に沿った捜査を展開していました。
捜査の結果、20人もの人々が被告人として裁判にかけられ、一審では5人に死刑判決が下され、控訴審でも4人の死刑判決が維持されるという厳しい判決が続きました。
しかし、最高裁では被告人らの自白の信憑性に疑問が呈され、差し戻し審では全員が無罪となった事件です。このように、松川事件は1つの事件で巻き込まれた人数が最も多い冤罪事件だといえるでしょう。
死刑確定後に再審で無罪となった代表的な事件
死刑が確定した後に再審で無罪となった事件の代表的なものとして、免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件が挙げられます。これらの事件はすべて1950年代頃に起きたもので、被告人たちの死刑が一度確定し、拘置所に収容されていたという点で共通しています。
これらの事件ではその後、再審請求が認められ、裁判のやり直しが行われた結果、4つの事件全てで無罪判決が下されました。再審では、自白が強要によるものだったことが明らかになり、一度確定された死刑が覆ったということで、松川事件よりも深刻度としては大きくなるでしょう。
近年の重大な冤罪事件:村木厚子さん郵便不正事件(2010年頃)
比較的最近の事例として、2009年に起きた厚生労働省元局長の村木厚子さんに対する郵便不正事件が挙げられるでしょう。郵便不正事件では、障害者用郵便割引制度の不正利用に、政治家とキャリア官僚だった村木さんが共謀加担したのではないかとの筋書きを検察が立てています。
この事件も結果的に無罪にはなるのですが、捜査・公判の過程で、検察官が証拠の改ざんを行ったことが明らかになり、検察幹部に逮捕者が出ています。逮捕者の中には、実刑が確定した人まで出るほどの重大事件です。
最終的に2010年村木さんは無罪判決を受けましたが、近年の事件では郵便不正事件が重大な冤罪事件として挙げられます。
KL:冤罪であることが判明し無罪判決が確定した後、真犯人に対して法的にはどのような対応がなされるのでしょうか?
水野氏:過去には、事件の重大さによって公訴時効が設定されていましたが、現在では特に重大な犯罪(例えば殺人など)については公訴時効が廃止されています。公訴時効がない場合、理論上は別の新しい事件として新たな捜査を開始し、真犯人に対して責任の追及が可能となります。
しかし、実際にはこのようなケースで真犯人が見つかり、処罰されたという事例をほとんど聞いたことがありません。というのも、時間経過による証拠の散逸や関係者の記憶が曖昧化するためです。
冤罪をなくすための改善案
KL:では、どうすれば冤罪を少しでもなくすことができるのでしょうか。また、そのためにどのような改革が必要だと考えられますか?
水野氏:冤罪をなくすためには、いくつかの重要な改革が必要だと考えられます。主な問題点と改革の方向性について説明します。
長期の身柄拘束と取り調べ
日本では、逮捕から起訴までの最大23日間にわたる長期の身柄拘束が許されているという実情があります。このような長期にわたる身柄拘束は、他の先進国と比較しても極めて長いものです。身柄拘束の期間中、被疑者は毎日長時間の取り調べを受けることになり、精神的圧迫や疲労から、実際には罪を犯していない人でも、虚偽の自白をしてしまうリスクがあります。
このような長期間の身柄拘束や取り調べは、多くの弁護士、心理学者らが指摘するように、被疑者に大きな心理的負担をかけ、やっていないのにやったと言わせてしまうような状況を作り上げることにつながります。
自白の重要性と問題点
また、日本の刑事裁判では、被疑者の自白が重要な証拠として扱われる傾向があります。しかし、長期拘束と取り調べにより得られた自白は信頼性が高いものだとは言えません。多くの冤罪事件では、このような状況下で得られた虚偽の自白が有罪判決の根拠となっています。
一度自白をしてしまうと、たとえ後に無実を主張しても、裁判官には「なぜ無実の人間が自白をするのか」という疑問が生じ、無罪を証明することが非常に困難になります。したがって、まずは、長期の身柄拘束と取り調べをどうにかしないと改革は難しいのかなと感じています。
また、現在世間で注目されている袴田事件の再審が始まりました。検察が改めて有罪の主張をし、理論上は再度有罪判決が出される可能性もあります。ただ、日本の再審では無罪の根拠となりうる新証拠がなければ再審が開かれることがないため、再審の裁判では無罪判決が下される可能性が極めて高いと言えます。冤罪の救済方法である再審についても、検察の持つ証拠がなかなか開示されないこと、再審の決定が出されても検察が異議申し立てを行う事ができることなど、様々な問題が指摘されています。
この袴田事件でもやはり、今とは比べ物にならないくらいの長期の過酷な取り調べにより、虚偽の自白をした可能性が指摘されています。
このように、冤罪の根本的な問題として、やっていないのに「やった」と言わされる状況が構造的に作られている日本の司法制度の仕組みにも問題があると思います。
冤罪に巻き込まれた場合の対応方法
KL:では、自身が冤罪に巻き込まれてしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
水野氏:はじめに、警察に疑われている場合、それは単なる疑いではなく、警察が本気で犯人だと思っているということを認識する必要があります。日本の警察は、基本的に優秀で職務にも誠実なため、逮捕や取り調べは真剣な疑いをもとに行われます。だから、「話せば分かってもらえる」という希望は捨てるべきです。
それに、警察や検察は職務上、被疑者がする弁解や言い訳を疑ってかかるわけで、冤罪事件に巻き込まれた場合は、弁護士(弁護人)が自分を助けてくれる唯一の存在だと認識してください。
したがって、できるだけ早く弁護士に連絡を取る必要があります。知り合いの弁護士がいない場合、初回は無料で相談できる「当番弁護士制度」の利用が可能です。その後の費用は当然かかりますが、お金がなくても弁護士がつけられるのは、逮捕後の勾留からなので、それでは遅すぎます。逮捕直後、手錠をかけられ、外部との連絡が48時間絶たれた状態で、弁護士をつけずに警察と対峙するのは事実上不可能だからです。
可能であれば、刑事事件や刑事裁判の経験が豊富な弁護士を選ぶことが望ましいといえます。自分が無実であることを、弁護士を通じて警察や検察に伝えることで、起訴猶予となり裁判に進まないケースも多くなります。
万が一、 裁判に進んだ場合、99.9%という高い有罪率の壁に直面します。このような状況で裁判に勝つためには、絶対に虚偽の自白をしないことです。どんなに追い込まれても、一度でも「やった」と言ってはいけません。一回でも自白すると、それが記録され証拠となり、後の裁判では非常に不利になります。
KL:では最後に、一度自白してしまった後でも、冤罪が晴れるケースはあるのでしょうか?
水野氏:一度自白してしまった後でも冤罪が晴れるケースは存在しますが、非常に困難な場合が多いです。日本の刑事司法システムでは被疑者の自白が非常に重要視されるため、警察や検察は自白を得ることに重きをおきます。
一度でも自白をするとすぐに書面化され、被疑者の署名・捺印が求められます。書面化された自白は重要な証拠になるため、後に弁護士が自白を撤回しようとしても、警察や検察はなかなかそれを認めようとはしないでしょう。
裁判で「やっていない」と証言しても、以前の自白と矛盾することになりますし、裁判所ではどちらの証言を信用するべきかという難しい判断を迫られます。しかし、一度自白をしている以上、裁判所は自白を完全に無視することはできず、多くの場合、自白が有罪判決の重要な根拠になってしまいます。
まとめ
日本の刑事司法制度における冤罪問題は、有罪率99.9%という驚異的な数字の背後に隠れた深刻な現実を浮き彫りにします。警察や検察の長期の身柄拘束や取り調べ、刑事手続の仕組み自体にも冤罪の原因はひそんでいます。特に、虚偽の自白が有罪判決の重要な証拠となる現行のシステムにも大きな問題があるといえるでしょう。
また、冤罪に巻き込まれた場合には、できるだけ早く弁護士に連絡を取り、虚偽の自白をしないことが最も重要です。弁護士の助けを借りて、無実を証明するための適切な手続きを踏むことが、冤罪から身を守る唯一の方法になると水野准教授もおっしゃられています。